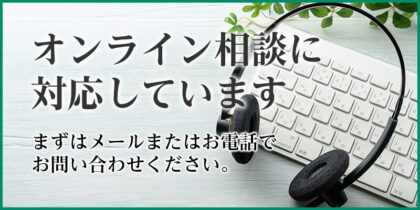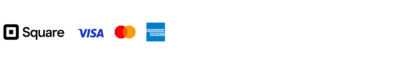![]()
高齢になり思うように身体が動かなくなったことから、自宅を売却し、息子夫婦と同居しようかと考えています。自宅は亡くなった夫から相続したもので、私たち夫婦はそこを拠点として農業を営んでいました。
売却のために知り合いの不動産業者に相談に行ったところ、私の自宅は用途変更の手続きをしなければ売却できないと言われましたが、どういうことなのかよく分かりません。
どうしてこのままだと家を処分できないのでしょうか。また、どのような手続きをすれば売却できるようになるのでしょうか。
![]()
お住まいの住宅は市街化調整区域にありますので、農家住宅として、開発許可の手続きをとらずに建築された可能性が高いです。農家であることを条件として、特別な許可を必要とせずに建築ができたことは覚えていらっしゃいますでしょうか。
そのため、この住宅を農家以外の方に売却したり、賃貸する場合には、農家住宅から一般住宅へと用途(使い方)を変更しなければなりません。この用途変更は都市計画法という法律による役所の許可が必要になります。
売却により建物の所有者が変わる場合には、誰もが買主になれる訳ではないので注意が必要です。買主には、少なくとも住宅または住宅の建築が可能な土地を所有していないことが求められます。
また、他人に貸す場合(賃貸住宅への用途変更の場合)には、相続によるものを除き所有者の変更は認められません。
開発許可が不要な農家住宅について解説
それでは、まず今のご自宅がどういう性質の建築物なのか、どういったいきさつで建築されたのか、私が想像できることをお話しします。
そもそも市街化調整区域では、建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更(これを「開発行為」といいます。)を行うことが禁止されています。都市計画法によって、市街化を抑制する区域と定められているからです。原則として建物を建てられないとお考えください。
しかし、開発行為を禁止している都市計画法第29条の例外として次のような規定があります。これに該当する開発行為については、許可が不要となっています。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(都市計画法第29条第1項第2号)
農林漁業を営む者とは、雇われている方、兼業の方を含みますが、臨時的に従事する方は含まれません。また、その地域で農業などを生業としている必要があり、これは世帯のうちの誰かが従事していればよいとされています。
ご相談者様はご夫婦で農業を営んでいたということですから、当然、農林漁業を営む者にあたります。そのため、農業を営むという条件付きで住宅を建てる際の開発許可が不要であったわけです。このケースでの住宅を一般に「農家住宅」と呼びます。
農家住宅から一般住宅への用途変更手続きについて解説
農家住宅を一般住宅へと変更するための手続きには、建物の所有者の変更がない場合と売却などにより所有者が変わる場合とで、許可の要件や手続きに必要となる書類が異なります。
※相続による所有者の変更は前者に含まれます。
一般に市街化調整区域では建物の用途変更が禁止されていますが、以下の要件に該当する場合には許可を受けることができます。
当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの(都市計画法施行令第36条第3号ホ)
福島県の場合、農家住宅を一般住宅へ変更するための許可の要件は、福島県開発審査会審査基準(令和4年11月25日改正後)の中で定められています。
建物所有者の変更がない場合
高齢になったなどのやむを得ない理由で農業を廃業した場合、農家住宅の条件を満たさなくなります。しかし、だからといって引き続きそこに住めなくなるのは不都合です。その代わりに、「住み続けるのはいいですが適切な手続き(許可)をとってください」という決まりになっています。
また、農業従事者が亡くなって、会社員など農業者以外の方が住宅を相続した場合も同様です。このケースについても、一定の手続きを経ることによって、相続した住宅に住み続けることが可能になります。
これらのケースでの用途変更の許可の要件は、福島県開発審査会基準第12号に基づくもので、次のとおりです。
- 用途変更の対象となる建築物は、適法に建築され、かつ、現在まで継続して適法に使用されたものであること
- 世帯内の農林漁業従事者の死亡等、農林漁業を廃業するにやむを得ない理由があること
- 用途変更後の建築物は専用住宅の用に供するものであること
- 建て替えまたは増改築を伴う場合の建築物の延床面積は、下表の規模以内であること
| 変更前 | 280㎡以内 | 280㎡超 |
|---|---|---|
| 変更後 | 280㎡以内 | 変更前と同程度 |
※ 延床面積280㎡以内の住宅の場合、車庫については45㎡を基準とし、主たる建築物とのバランスにより判断されます。また、その他の付属建築物については1つの用途につき30㎡以内と定められています。
建物所有者の変更を伴う場合
今回の相談事例のように用途変更に伴って所有者が変わる場合には、用途変更の許可のハードルが上がります。また、このケースでの許可要件は、分家住宅から一般住宅への用途変更と共通するものとなっています。
こちらについては福島市の開発審査会基準(包括承認基準第3号)を参照しながら、許可の要件を確認していきましょう。農家住宅または分家住宅を一般住宅に用途変更するためには、次の①~④のすべての要件をクリアすることが必要です。
①用途変更の対象となる建築物は建築基準法に適合しており、次のいずれかに該当する住宅であること
- 都市計画法第29条第1項第2号に該当する農家住宅であること
- 都市計画法第34条第1号に該当して許可を受けた店舗兼住宅であること
- 都市計画法第34条12号に該当して許可を受けた分家住宅であること
(以下省略)
②用途変更する事由について、次の(1)または(2)のいずれかに該当すること
(1)線引き後に適法に建築された後、10年以上適正に使用された住宅であること
(2)線引き後に適法に建築された後、適正に使用された期間が10年未満の場合、下記のいずれかの理由が認められること
- 死亡・後継者不在により使用継続が困難であること
- 離婚により使用継続が困難であること
- 通勤が不可能と認められる転勤・転職により使用継続が困難であること
- 負債処理及び破産により使用継続が困難であること
- 倒産または廃業により使用継続が困難であること
- 高齢または疾病により使用継続が困難であること
- 裁判所による競売により使用継続が困難であること
- 自己居住用として20年間使用された住宅であること
③面積要件
用途変更後の建て替えまたは増改築を伴う場合の建築物の床面積は、280㎡以内であること。なお、車庫については45㎡以内であり、その他の付属建築物については一の用途につき30㎡以内であること
④許可申請者の要件
- 申請者は申請する建築物を取得しようとする者であること
- 申請者は申請する建築物以外に居住用資産(住宅や住宅建築可能な土地)を所有していないこと
市街化調整区域の農家住宅・分家住宅を一般住宅として所有しようとする場合には、取得しようとする住宅以外に居住用資産がないことが求められます。転売目的や資産保有目的での取得を防止し、不動産取引を最小限に抑えるためであると考えられます。
ただし、福島県においては「県外からの二地域居住の場合はこの限りではない」とする例外規定があります。他県に住宅などを所有している場合であっても、福島県内に住宅等がなければ、農家住宅・分家住宅を一般住宅として取得できる可能性があります。
用途変更手続きに必要な書類
最後に、所有者の変更が伴う場合の農家住宅から一般住宅への用途変更について、都市計画法に基づく許可申請に必要な書類をご案内します。以下で提示する書類は福島市で求められる書類ですが、これは分家住宅からの用途変更とも共通するものです。
- 許可申請書(様式あり)
- 位置図(縮尺1:25000 都市計画総括図に申請地を表示すること)
- 区域図(縮尺1:2500 都市計画図に申請地及び接する道路名を表示すること)
- 公図(法務局に備えつけのもの)
- 土地全部事項証明書(必要に応じて閉鎖登記簿謄本)
- 建物全部事項証明書(必要に応じて閉鎖登記簿謄本)
- 申請に係る土地・建物を取得することを確認する書類(不動産売買契約書など)
- 開発行為同意書(開発行為を伴う場合)
- 住民票(申請者世帯全員分)
- 売主などが10年以上居住していたことが確認できる書類
- 戸籍謄本(売主側の所有者が相続により変わっている場合)
- 名寄帳または無資産証明書(申請者世帯全員のもの)
- (分家住宅の場合)開発許可時の許可証・検査済証
- (分家住宅の場合)開発許可時の設計図書
- 新築・増築時の建築確認通知書及び平面図・立面図
- 売主側の説明書(申請に係る建築物のこれまでの使用状況を記載)
- 申請者からの申立書(申請に係る建築物を必要とする理由を記載)
- 念書(自ら居住し、賃貸、用途変更をしない旨を明記する)
- 事前協議の回答書(事前協議を行っている場合)
- 現況図及び現況写真
- その他市長が必要と認める書類
まずご理解いただきたいのは、所有者の変更が伴う用途変更は、申請者は新たに建物を取得しようとする者(買主など)になるということです。しかし、必要となる書類の中には売主側が提供しなければならないものも含まれています。
また、ご覧いただいたとおり、かなりの分量の書類を準備しなければならないことがお分かりかと思います。一般の方がご自身で用途変更手続きを行うことはなかなか難しいといわざるを得ないでしょう。
なかなか難しい市街化調整区域の不動産の活用
都市計画法によって、市街化調整区域に区域区分されている土地やそこにある建築物には、その利用について強い規制がかけられています。この相談事例のように、開発行為や建築行為を伴わない用途変更であっても許可が必要になります。
農家住宅や分家住宅は、建築した当時の申請者の属性に注目して特別に建築が許された建築物です。そのため、これを一般住宅に用途変更して誰もが居住できるようにすることは、都市計画法の趣旨に反するものといえます。
市街化調整区域の建築物の取扱いについては様々な規制がありますので、何らかの変更をしようとする場合には、事前に役所の担当部署に相談することをお勧めします。なお、福島県での手続きについては、どうぞ当事務所にご相談ください。